
~前回のあらすじ~
13年前の30歳の頃、写真表現を学び始めたパンダさんは、
1年目の展示作品を考察してみるのだった。
そして2年目の本科コースについて、振り返る…。
写真表現について考える②~写真で思いを表現できるなんて目からウロコ~ | パンダさんのブログ
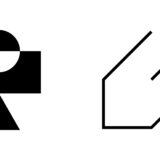
【第24期 写真表現大学 本科】
- 受講期間:2012年4月~2013年3月 隔週日曜
- 概要:テーマを持って作品制作を進めていくコース
- 内容:撮影の基礎、映蔵史、ライティング(静物、人物)、特別講師による特別講義、作品制作、作品の合評、ギャラリー展示
そうして私は、写真表現大学の初心者コース「プレ・フォトスクール(全10回)」を修了し、1年間の本科(月2回程度)に通い始めた。

ちなみにコース改変があり現在とは異なるが、当時は私が通う月2回の本科とは別に、週2回のプロカメラマンコース、週2回の総合科があった(計30人ぐらい)。
プロカメラマンコースはその名の通りプロカメラマンのテクニックを習得したい人向けで、総合科は写真作家を目指すコースである。働きながら週2回を1年間、つまり毎週土日を授業に費やすので、相当気合の入った人たちである。

総合科の人達とは同じ授業を受けるし、ライティングなどプロカメラマンコースの人と同じ授業もあったので、コースは違えど自然とみんなと仲良くなり、今もつながっている人がいるのは嬉しい♪
さて、授業は映像史などの座学から始まり、撮影の基礎やプロも使う機材を用いたライティングなどの実技へと進んでいった。
映像史の授業の中で、講師の印象に残っている言葉がある。
世界的なピアニストや世界で活躍する野球選手など、音楽やスポーツですばらしい功績を上げるには、「技術」の鍛錬が必要で、幼い頃から続けている人の方が有利な場合が多い。しかし、
写真表現はいつからでも始められる!

写真は、カメラの操作方法さえ覚えれば誰でも撮影が可能である。もちろんライトの当て方や絞り、シャッタースピードの調整などに技術はいるが、カメラの性能が上がったことで、簡単にキレイな写真が撮れるのだ。しかも近年のスマホカメラの機能や画質はすさまじく、調整のいる一眼レフよりむしろキレイに撮れたりする。

つまり「写真表現」は、技術の鍛錬に時間をかけるというより、「何を写して何を表現するのか」ということを問われる分野なので、むしろ大人になって思考能力が上がり、世間に揉まれ社会に対する思いや感情も複雑になることで、表現が深くなるとも考えられる。幼い頃からの技術の鍛錬もあるに越したことないが、そういったものがなくても写真表現はできるというのである。
(商業写真はまた別。)
大人になってから始める人にとって、
その言葉、しびれる~~!

そういった授業を受けながら、自身の撮影を続けて、自分自身のテーマを深掘りしていった。
制作を進めるにあたり、「撮影計画」を立てる方法も教わった。自分のテーマを表現するための撮影方法について計画を立て、実行するのである。
【撮影計画書の項目】
- テーマ(主題)
- コンセプト(内容)
- アプローチ(撮影方法)
- メディア(機材・フィルムなど)
- フィニッシュ(発表方法)
- スケジュール
- 資料
例えば1.テーマが「いのち」だったとすると、もう少し掘り下げた内容を2.コンセプトに書き、では何をどう撮るのかを3.アプローチに書いて、それを撮るにはどんな機材を使うのかを4.メディアに書き、5.フィニッシュにそのテーマを表現する展示や発表方法を書いて、撮影スケジュールを6.スケジュールに書くイメージである。

ただこれ、自分のテーマありきの考え方なので、テーマがすでに決まっている人はいい。
受講生の中には、例えば「食について考えたい」などすでにテーマが決まっている人や、「消波ブロック(いわゆるテトラポッド)」「うさぎ島」などすでに撮る対象が決まっている人もいた。中には、「写真を和紙に印刷する」と、印画方法から逆算して撮影対象を決めている人もいた。
しかし、テーマが決まっていない私のような人にとっては、そもそもテーマを見つけるにはどうしたらいいの?となる。そのヒントとして教わったことは、
自身の撮った写真を印刷して、机に並べて観察すること。

普段何気なく撮った写真データを、L版などの写真用紙に印刷し、大きな机に並べてみて、自分の傾向や好み、気になることを探るのである。確かに印刷した方が一覧性があるし、カテゴリーごとに並べ替えることも簡単にできる。
私の場合、記録的に家族や友人を撮ったもの以外は、青空や夕暮れ、路地、光と影、草木など、人以外の被写体が多い。ぱっきりとコントラスト強めの写真や、夕暮れのような露出を抑えた暗めの写真が好きである。
その中で自分自身が最も気になったのは、やはり「夜道」の写真だった。前年の修了作品の時と同じで、夜中に出歩いた時に見る灯りや灯りに照らされてぼんやり浮かび上がるものに惹かれた。単に好きというより、なんだか「ヒリヒリ」した感じもする。

これをテーマにしよう!と思ったものの、さぁ、ここからまたさらに悩み始めるのである。
なぜ夜道が好きで、何を表現したいのかが、分からないのである。

ある時授業の中で、特別講師による作品講評の時間があった。受講生それぞれが制作途中の写真を机に広げて講師が見て回り、みんなの前で講師が評価コメントを言うのである。
その講師はあまり褒めないことで有名(?)なタイプの写真家だったので、怖いながらに私は、まだ選別していない多数の夜道の写真を広げて、「夜道の街灯の光にずっと惹かれるものがあって…」と説明した。まぁ、確かに説明らしい説明にはなっていないが、その際講師からは、「街灯の光には、誰でも惹かれるよね」というコメント以外はもらえなかったのである。

そしてその講師は、別の受講生の「奇妙なものを撮った」という作品について、「なかなかよく撮れている」と言って、凝視していた。確かに写真のうまい人だった。普段の生活の何気ない風景や人物なのに、モノクロ写真なのも相まって、確かに「奇妙」な雰囲気が表現できていた。ただ私は、
奇妙だからどうなの!?
と思ってしまい、ますます「テーマ」や「表現したいもの」の関係性が、よく分からなくなったのである。

今ならなんとなく、写真で切り取ることで人間の奇妙性、多面性を掘り下げるみたいな意味があったのかな~?と思えるが、当時はそこまで考えが回らなかった。
当時の撮影計画書を見てみても、私の葛藤がうかがえる。
1.テーマ
- 闇と光
- 夜道、路地の街灯・蛍光灯
- 暗闇に浮かび上がる(照らし出される)道・路地
- 暗闇の中かすかな光に照らされて続いている道
- 夜を暗く撮る
- 夜道に浮かび上がるもの
- 古びたものが夜道の街灯・蛍光灯に照らし出されている様
- 古びたものが夜に放つ魅力、怖さ
- 闇の中の光
- 光?あかり?闇?道?コントラスト?公園、街灯、建物
- 現実逃避の気持ち、内に内に行く気持ち
- 想起する気持ち。せつなさ、さびしさ、疲れた、明日になってほしくない
2.コンセプト(内容)
- 根底にあるもの
作品を発表して自分をさらけ出すことで、自分を救いたい。自分を変えたい。 - 自分をさらけだす
自分の日常をスナップ的に切り取るというより、抱えている闇に迫るようなものを撮りたい。それを撮る行為。自分を知られることも、さらけ出すということ。 - 闇
正体がよく分からないもやもや。現実逃避。夜の道に共鳴する心。闇に浮かぶ光に惹かれる気持ち。アニメ。家の中。受け身。 - 撮る対象、見る人へのメッセージ
- 闇について考える

テーマには、テーマというより撮影対象のことが書かれていて、堂々巡りしている。ただ、特にコンセプトを読むと、現実逃避している自分をさらけ出すための作品であることはよく分かる。
当時、夜中まで仕事をしても報われないという気持ちがあり、環境のせいにしたり自分の性格をうらんだりして、明日になるのが怖くて夜更かししてアニメを見ていた。そんな自分をさらけ出すことで、自分自身を救いたいという想いがあったのである。
ただ、ではなぜ夜道の街灯なのか?という問いには、はっきりした言葉で説明できない。夜道を自身の闇の部分と捉えて、その中に佇む街灯の光にほのかな希望を見出している…のか?

悶々とした気持ちを引きずりながら作品制作を進めていったが、ある時私は、
撮影に行くことが怖くなってしまった。

ちなみにこの夜道の撮影は、人の少ない時間帯の0時以降に一人で行っていた。大阪は終電が遅く夜も人が歩いていたりするものの、やはり暗闇は怖いものだ。ただそれ以上に恐らく、これを撮っても意味を見出せないことが怖かった、のだと思う。たぶん。
ある意味で「作品制作をする意味があった」とも言えるが、苦しみの方が大きくなってきた。

そんな頃、特別講師による2回目の作品講評の授業があった。前回と同じ講師だったかは忘れてしまったが、キレッキレの写真家が来ると聞いていた。私はその授業を、
サボってしまった!

私はついに、
逃げ出した!

どうなるパンダさん!
次回は恐らく最終回!

写真表現について考える④~人に気づかされた自分の思い~ | パンダさんのブログ
【参考】私の撮影計画書の続き
3.アプローチ(撮影方法)
- 人気(ひとけ)のない時間帯(0時以降)の夜の道を撮る
⇒家の近所の路地、翌日休みの日 - ぶれないように三脚を立て、感度はISO100くらいで粗さを出さない
- 三脚を低くして違和感を出す(自分の目線とは違う)
↑先日撮ったらおもしろい感じになった - 適正露出より2段ほど下げて闇を強調すると同時に、光を浮き上がらせる
- 絞り開放で中心を際立たせる
4.メディア(機材・フィルムなど)
- デジタル一眼(CANON EOS Kiss X5)
- 50mm単焦点レンズ
5.フィニッシュ(発表方法)
- 4~6点ほどを横に並べる
- 大きさ:未定
- 黒縁フレーム、白マット
- マットっぽいプリント
6.スケジュール
- 主に土曜日の晩など、翌日仕事が休みの日の晩に撮る
7.資料
- 谷崎潤一郎「陰翳礼讃(いんえいらいさん)」中央公論社、1995年改版
陰影、陰陽、光と影の描き方
闇とは何か、影とは違う、本当の闇は今の世になかなかない

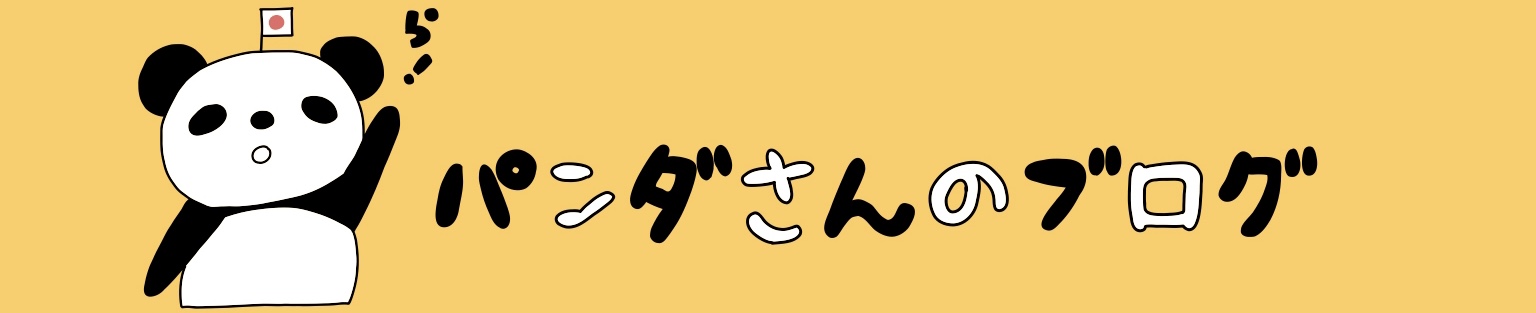


コメント